ふとん大学(話題の本を紹介!)
【全米ベストセラー】回復人 体中の細胞が疲れにつよくなる【10分で要約】
391 回視聴 2024/03/15
1.疲労の原因はミトコンドリアにある
・人間の体が持つ細胞を全て
500~2000個のミトコンドリアが含まれる
細胞が働くのに必要なエネルギーを作る
・ミトコンドリアが正常に働かない ✖
細胞がエネルギー不足となる
これが疲労の原因
・ミトコンドリアはストレスのセンサー
細胞を守る働きもしている
防御に徹するとエネルギーを作れない
→ エネルギー不足に陥る
・ミトコンドリアを機能不全にするストレス
⑴ 炎症
⑵ 酸化
⑶ 細胞破壊
2.ミトコンドリアの劣化を防ぐ方法
・2種類の体内時計
⑴ 脳の体内時計
⑵ 体の体内時計
→ 外的要因によってセットされる
例 光
気温
運動
食事 など
・太陽の光で体内時計はセットされる
日の出と共に起きる
日の入りと共に寝る
→ ほとんどの人ができていない
体内時計がズレてしまう
睡眠の質が低下する
ミトコンドリアの劣化を招く
・睡眠の質の低下
マイトファジーの減少を招く
・マイトファジーとは?
新しいミトコンドリアを再生すること
マイトファジーは睡眠中に起こる
・睡眠の質を上げる方法
何を食べるかよりもいつ食べるかが大切
・適切な食事の方法
⑴ 食事の時間枠を決める
⑵ 食事をとる時間を決める
夜のカロリーを減らす
⑶ 早い時間にカロリー多めにとる
⑷ 食事に一貫性を持たせる
同じパターンで食べる
・食事の時間枠を決める
夜の間に長めの絶食時間をとる
全ての食事を6~10時間の枠内でとる
→ 概日リズムを整えられる
・食事をとる時間を決める
夕食にとるカロリー量が多い ✖
エネルギーレベルを下げてしまう原因
→ 概日レベルのズレにつながる
夕食にとるカロリーを減らすべき
・早い時間にカロリー多めにとる
食事の大部分を朝と昼にとる
健康な代謝活動が進む
→ エネルギーレベルが上がる
朝起きた時にエネルギーが高まる
概日レベルを整えられる
・食事に一貫性を持たせる
概日リズムは起こることを予測して動く
食べる時間がバラバラ ✖
→ 概日リズムがくるう
なるべく同じ時間に食事をとるべき
・昼食と夕食にタンパク質を多くとる
睡眠の質を上げられる
「!」の多いふとん大学さんです。今回の作品からは「全ての食事を6~10時間の枠内でとる」が参考になりました。私は16時間断食を意識しています。ミトコンドリアにも良い影響があるとわかりました。
サムの本解説ch
【13分で解説】回復人 体中の細胞が疲れにつよくなる
3,137 回視聴 2024/04/06
1.体内時計を修復する
①自然のリズムが人体に深く影響する
②時計を決める4つの要素
③環境と行動を整える
①自然のリズムが人体に深く影響する
・7~8時間の睡眠が必要
これより少ない睡眠は健康に害を及ぼす
例 心血管
代謝
精神面
免疫機能
身体能力 など
・約30%が6時間以上の睡眠を取れていない
多くの人が睡眠に問題を抱えている
体内時計の機能不全が原因
・体内時計は様々なものをコントロールする
例 気分
やる気
体脂肪
代謝
ホルモンのリズム
神経伝達物質のバランス
細胞再生
睡眠の質
ミトコンドリアの健康 など
②時計を決める4つの要素
・24時間の太陽の周期が影響する
体内時計の2つの構成要素
⑴ 脳の時計
体の反応を調整する
ホルモンと神経伝達物質で行う
⑵ 体の時計
細胞レベルのプロセスを調整する
・体内時計に影響する4つの要素
⑴ 光
⑵ 気温
⑶ 運動
⑷ 食事
③環境と行動を整える
・睡眠衛生を向上させる方法
⑴ 遮光シェードを使う
寝室を暗くする
⑵ 寝る1時間前に熱いシャワーを浴びる
風呂に入って体温を上げる
⑶ 寝る1時間前は電子機器を使わない
ブルーライトカットのメガネをかける
⑷ 寝る直前20分前の行動を整える
日記をつけたり瞑想したりする
・栄養について
⑴ 食事の時間枠を決める
なるべく短い時間枠にすべき
絶食時間が長い
→ エネルギーレベルが上がる
例 食事時間枠
10時間以内
夕食から翌朝の朝食まで
14時間絶食
⑵ 食事をとる時間を決める
なるべく毎日同じ時間に食べる
⑶ 早い時間にカロリーを多めにとる
食事の大部分を朝食と昼食でとる
代謝活動の促進
代謝能力の向上
⑷ 食事に一貫性を持たせる
2.腸の壁の修復
①腸に住む40超の微生物を味方につける
②いい細菌に食事を与える
③食物繊維は多様に摂るのがベスト
①腸に住む40超の微生物を味方につける
・全ての病気は腸から始まる
腸の健康=微生物叢の健康
・微生物叢とは?
腸内フローラとも呼ばれる
数兆個の微生物の群のこと
・人によって細菌パターンが異なる
細菌の多様性が健康を決める
⑴ 善玉菌
代謝と栄養素の産生を向上
免疫系に情報を与える重要な役割
⑵ 悪玉菌
増殖する原因
生活のストレス
抗生物質
食物繊維不足
増殖すると健康問題が発生する
②いい細菌に食事を与える
・細菌には食物繊維が必要
多くの人が食物繊維不足
例 1日に摂る食物繊維の量
現代のアメリカ人
1日16g
旧石器時代の祖先
1日45g
③食物繊維は多様に摂るのがベスト
・急に食物繊維を多くとる悪影響
例 膨満感
ガス
胃痛
便秘
下痢 など
・FODMAP(フォドマップ)とは?
小腸内で消化・吸収されにくい糖類の略称
減らしても解決手段にはならない
→ 微生物にダメージを与えるだけ
・微生物の乱れを改善する方法
⑴ 多種多様な高繊維をとる
⑵ 発酵食品もとる
3.糖を食べて疲れない
①血糖値の波をならす
②血糖値が10秒で改善する方法
①血糖値の波をならす
・血糖値が安定しない ✖
激しい疲れを覚える
血糖値を安定させるべき
・血糖値を決める2の要素
⑴ 何を食べるか
⑵ 体脂肪
②血糖値が10秒で改善する方法
・食事前に酢を大さじ1杯飲む
血糖反応全般が11%減少
インスリン反応が16%減少
→ 血糖コントロールを改善する
・酸っぱい成分が影響する
消化を遅らせる
消化酵素の働きを抑制する
→ 食後の血糖値の上昇が穏やかに
・オススメの方法
サラダや野菜にかけて食べる
大さじ1~2杯のお酢
→ オリーブオイルと混ぜてかける
論理のサムさんです。今回の作品からは「お酢が血糖コントロールを改善する」ことを初めて知りました。私は黒酢を水で薄めて飲んでいます。食事のときに必ず飲むようにしようと思いました。
今日のアクションプラン
食事のときに黒酢ドリンクを飲む
今日のアクションチェック
私は黒酢ドリンクは、サウナの水分補給のときに飲むことにしています。
もちろん、食事のときにも飲めば体に良いことは分かります。
しかし、昼食には味噌汁があり、夕食にはハイボールがあります。
飲み物があると、黒酢には手が出ないです。
でも、1回試してみようと思いました。


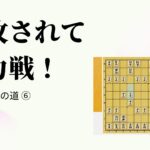
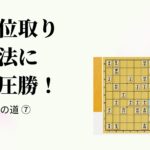
コメント